2004年から始まったこのコラムも、20回目になりました。これからも分科会活動の報告や、皆様への私からのメッセージを伝えていきたいと思いますので、お付き合いをよろしくお願いいたします。
さて、今年のクライアント管理分科会では「ソフトウェアライセンス管理のプロシージャを作ろう!」というテーマで議論を重ねているのですが、今回は、その議論の過程で感じていることをお話しましょう。
ソフトウェアライセンス管理の基本の考え方は、
使用しているソフトウェアの数 ≦ 所有しているライセンス数
という状態を維持することです。企業などの組織において、どのような管理を行えば、この状態を維持できていることを担保できるか?という発想から、分科会ではプロシージャを作ろうとしているわけです。
管理の対象となるのは、大きく次の2つになります。
・使用しているソフトウェアの数
・所有しているライセンスの数
それぞれについて現状のたな卸しを行い、その後は、それぞれの増減を管理していけば良いわけです。
前者の方は、動かしているコンピュータの数が少ないのであれば、運用管理者の手で直接調べることもできます。コンピュータの数が多いのであれば、半ば自動的にソフトウェアの種類と数を集約してくれるシステムを導入することもできます。ユーザが無断でソフトウェアを導入してしまうような事態に対しては、それを禁止すると共に「定期的に強制調査する」ということを周知しておけば良いでしょう。
問題は後者の「所有しているライセンス」を管理することです。ちょっと考えてみるとわかりますが、あまりにもその取得手段・入手ルートが多すぎるのです。会社の購買部門を経由してソフトウェアを購入した場合は、そこで集約することもできるかもしれません。しかし、それをすり抜けるルートが多すぎて困るわけです。
・購入したパソコンにソフトウェアがプリインストールされていた。
・部門が経費でソフトウェアを購入してきて、勝手に使っている。
・業務システムをSIerに発注したら、納品物の中に商用ソフトウェアが含まれていた。
・そもそも、今まで何も管理していなかったので、ライセンスに関する資料が四散している。
こうした状況に「ライセンス違反」が重なることは容易に想像できるでしょう。ソフトウェアを1本しか購入していないのに、部門のほとんどのパソコンで動いている、などという状況が生まれます。
そんな部門に、ソフトウェアの使用数とライセンス数を報告させても、正しい数字が返ってくるとはとても思えません。そもそもライセンスに関する意識が低いために、報告書の中でだけ辻褄が合うように、虚偽報告されるのが関の山でしょう。
そういえば、日本漢字能力検定協会が選んだ2007年を表す「今年の漢字」は、『偽』でした。まあ、出るわ出るわ。食品の産地偽装、土産品の原材料偽装。賞味期限改ざん。耐震偽装問題など、とにかく2007年の1年間で、日本人の多くは「何を信用したらいいのか?」という問題と向き合うことになりました。
この問題は他人事とは思えません。ソフトウェアライセンス管理に携わる私達も、ライセンスの契約相手を欺いたり、虚偽報告を鵜呑みにしたりしないような仕組みを、しっかり考えていかねばなりません。
そういえば、評論家の山本七平氏(1991年に死去)が自らの軍隊体験を綴った「一下級将校の見た帝国陸軍(朝日新聞社、1984年)」の中で、軍隊が「員数主義」に如何に蝕まれていたかを紹介していました。ここで言う「員数」とは物品などの数を意味していますが、帝国陸軍の場合、員数検査があまりにも形式主義に陥っていたそうです。すなわち「員数が合わなければ処罰」「員数が合ってさえいれば不問」なので、書類上の員数検査結果が合っていればそれで良く、それを合わせるためであれば「盗み」や「嘘」ですら公然の秘密であったとのことです。
こうした形式主義は、現代の企業の中にも生き残っています。筆者も実際に経験していることです。それは1999年のことでした。ちょうど、コンピュータの西暦2000年問題が世間を騒がせていた頃のことです。取引先からは「貴社の西暦2000年問題への対応は完了していますか?」という確認が続々と寄せられました。このあたりのお話は、第16回WEBコラム「IT内部統制対応と、どう向き合うか」でもご紹介しました。
もちろん取引先には「対応中であり年末までには完了の予定」とか、「100%対応を完了した」などと返答します。しかし現実には、その返答を出した翌日には、新たな問題が発覚しているのです。それが年末までに対応を完了できるかどうかを、新たに検討しなければならないのです。今から考えれば、明らかに取引先への虚偽報告でした。
しかし、社内には「できるだけの事はやってるんだから、しょうがない。お互い様だよ」という雰囲気があったと思います。挙句の果てに、各種の報告書類だけは、つじつまが合うように作成していました。現実はまた別問題だったのです。
この姿は、山本七平氏が語った帝国陸軍の「員数主義」と同じではないでしょうか。現実は現実、書類は書類だという考え方です。食品の原材料偽装などの事件の裏には、これと同じ構図の問題が潜んでいたかもしれません。
織田裕二は『踊る大捜査線』の中で「事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ!」と叫びます。これも読み替えれば、書類だけを集めて議論していても員数主義に陥るだけということです。本当は現場の姿が、正しく書類に記載されていればいいのですが、なかなかそうはいかないようです。
今までに私は、第10回WEBコラム「何が信用できるか?」、第11回WEBコラム「疑うことを知らない?」などを通じて、偽装などにどう身構えたらいいのかをお話してきました。しかし、他人を疑うだけではだめなのです。私たち自身や勤めている会社も、特に書類やデータが『偽』に染まらないことを、再度確認する必要があります。また、大切なのは、そうした『偽』を起こさせない仕組みを作っていくことです。それこそが、今年の分科会テーマなのですね。正しい情報が入手できれば、それを正確に処理することは、ITの得意とするところです。
筆者は、Y2K問題への対応作業について、こう考えていると、16回のコラムで書きました。
「Y2Kは企業全体どころか日本全体、世界全体の問題であり、何らかの対処は必ず実行しなければならない。そうならば、その副次効果が自分の担当業務にとって、ひいては自社にとって有利になるように実行しよう」
今回のテーマである、ソフトウェアライセンス管理も同じだと思います。後ろ向きに仕方なく管理するのではなく、コストダウンのネタを集めるつもりでやっていこうではありませんか。
第二回クライアント管理分科会(大阪)は2007年12月19日に開催されました。前回と同様に、グループワーク形式で、しっかりと議論していただきました。参加いただいた皆さまからの掲載許可をいただきましたので、写真でその雰囲気を見ていただきます。
会場に20人以上が集まりますと、どうしても発言に偏りが出ます。しかしワークグループに分かれますと、ぐっと話やすくなり、ほぼ全員がわいわいと意見を出し合う場になります。この熱気は、そのまま懇親会へと流れていくのでした。
まだ、分科会へ参加したことの無い方も、ぜひ気軽にお越しください。盛り上がって、やる気が起こること請け合いです。
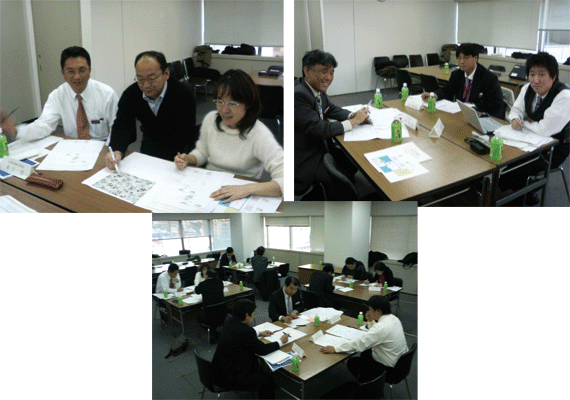
パーソナルコンピュータとの付き合いは1979年のNEC社製PC-8001から始まっています。
1985年から当時はオフコンと呼ばれていたIBM社のシステム36を使って、機械製造メーカでの社内用生産管理システムの構築に関わりました。言語はRPGでした。
1990年ごろから社内にパソコン通信やLANを導入してきました。この頃からネットワーク上でのコミュニケーションに関わっており、1993年以降はインターネットとWindows NTによる社内業務システムの開発、運用を行ってきました。
1996年からはインターネット上でのコミュニティであるNT-Committee2に参加し、全国各地で勉強会を開催しています。
http://www.hidebohz.com/Meeting/
1997年からはIDGジャパンのWindows NT World誌に「システム管理者の眠れない夜」というコラムの連載を始めました。連載は既に7年目に突入し、誌名は「Windows Server World」に変わっていますが、読者の皆さんに支えられて今でも毎月、締め切りに追われる日々が続いています。
連載から生まれたメーリングリストもあります。ご参加はこちら。お気軽にどうぞ。



Copyright 2008 Hideki Yanagihara All Right Reserved