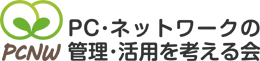2025年11月6日
- トップページ
- 情シスのHonne!
- ブレンドコーヒーに学ぶ、チームの多様性マネジメント
ブレンドコーヒーに学ぶ、チームの多様性マネジメント

はじめに
日に日に寒さが増し、温かいコーヒーが恋しい季節になりました。オフィスでも、デスクに湯気の立つマグカップを置いて仕事をする光景が増えてきたのではないでしょうか。この季節、私はいつもより時間をかけてコーヒーを淹れるようになります。寒い朝に飲む一杯は、心も体も温めてくれる特別な存在です。
さて、情シス部門のマネジメントにおいて、「多様性」は避けて通れないテーマです。今日は少し視点を変えて、私の趣味であるコーヒーのブレンドから、チーム運営のヒントを考えてみたいと思います。
ブレンドの本質とは
私が最近ハマっているのは、異なる産地の豆を組み合わせたブレンドコーヒーです。単一産地の豆(シングルオリジン)も魅力的ですが、ブレンドには独特の奥行きがあります。例えば、フルーティーな酸味を持つエチオピア産と、チョコレートのようなコクを持つブラジル産を組み合わせると、甘さと苦味のバランスが絶妙な一杯が生まれます。面白いのは、個々では平凡な豆でも、適切に組み合わせることで、想像以上の味わいが生まれることです。
ただし注意点があります。あまりに多くの豆を混ぜすぎると、個々の特徴が相殺され、平坦で特徴のない味になってしまいます。大切なのは、各豆の個性を活かしながら、全体としての調和を生み出すことです。
IT部門における「ブレンド」の難しさ
この原理は、情シス部門のチーム構成にも当てはまります。私たちの部門には、インフラエンジニア、セキュリティスペシャリスト、ヘルプデスク担当、プロジェクトマネージャーなど、異なる専門性を持つメンバーが集まっています。それぞれが高い専門性を持っていても、ただ集めただけでは最高のパフォーマンスは発揮できません。
特に大規模な組織では、個性が埋もれがちです。標準化やプロセス重視の風土が強すぎると、メンバーの独自の視点や創意工夫が失われてしまいます。一方で、各自が好き勝手に動けば、統制が取れず、組織としての力を発揮できません。
実践例:多様性が生んだ解決策
以前、社内システムのUI改善プロジェクトで印象的な経験がありました。当初、エンジニア視点では「機能は十分、改善の必要なし」という結論でした。しかし、ヘルプデスク出身のメンバーが「ユーザーからの問い合わせを分析すると、特定の画面で迷う人が多い」というデータを提示。さらにデザイン経験のあるメンバーが「情報設計を見直せば、問い合わせ自体を減らせる」と提案しました。
結果として、三者の視点を組み合わせることで、単なるUI改善にとどまらず、業務フロー全体を最適化するソリューションが生まれました。問い合わせは30%減少し、ユーザー満足度も向上しました。
これは、異なる専門性と経験を持つメンバーが、それぞれの「個性」を発揮した結果です。
多様性を活かすための3つのポイント
私の経験から、チームの多様性を活かすには以下が重要だと考えています。1. 各メンバーの「強み」を明確にする
誰が何を得意とするのか、チーム全体で共有します。技術的な専門性だけでなく、「ユーザー視点で考えられる」「データ分析が得意」といった特性も含めます。
2. 「違和感」を歓迎する文化をつくる
多様性の価値は、時に「違和感」として現れます。「その視点はなかった」という気づきこそ、イノベーションの源泉です。異なる意見を出しやすい心理的安全性が不可欠です。
3. プロセスを楽しむ
ブレンドコーヒーの配合を考えるように、最適なチーム編成や役割分担を模索するプロセス自体を楽しむことで、試行錯誤から学びが生まれます。
まとめ:システムと人間のバランス
情シス部門は、システムやプロセスの標準化を重視しがちです。それは確かに重要ですが、同時に人間の多様性を活かすマネジメントも必要です。ブレンドコーヒーのように、個々の特徴を残しながら全体としての調和を生み出す。そのバランス感覚こそが、これからの情シスリーダーに求められるスキルではないでしょうか。
寒い季節は、チームメンバーとゆっくり話す時間を作るのにも良い時期です。温かい飲み物を片手に、それぞれの強みや課題について語り合う。そんな時間から、新しい気づきが生まれるかもしれません。
あなたのチームは、どんな「ブレンド」になっていますか?一度、コーヒーでも飲みながら、考えてみてはいかがでしょう。
| 森 厚 | 積水ポリマテック株式会社 システム企画課 |
制御系ソフト開発会社に入社し、主に鉄道関係の制御ソフト開発にSE・PGとして従事する。
2004年からは車載機器メーカーに出向し通信制御のソフト開発に携わるが、出向先の業務縮小のため2013年に帰任。
社内では情シスとしてセキュリティとインフラを担当。現在は総務人事部に席を置き、社内IT教育やグループウェア等の導入はじめとした、ITを用いた業務効率化を担う。